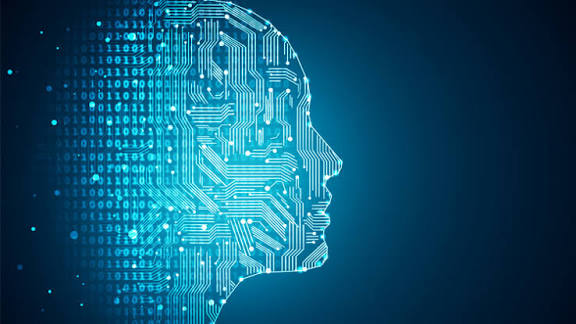情報社会、どのダイエット情報が真実なんだろう?
NEWS
2025 / 10 / 29
最終更新日:2025年10月29日
こんにちは!BEYOND登戸店です!
今回は情報の取捨選択についてお話ししていきます!
現在いつでもどこでも筋トレやダイエットなどのボディメイク情報を取得することができますが、どの情報が真実で、どの情報を信じればいいのかわからない!という方に向けたお話をしていきます🔥
今回の話を聞いていただければ、より正確な情報を手に入れやすくなると思います👍

目次
情報源の多様化

情報源の多様化。技術的要因
情報源が多様化した最大の要因は、テクノロジーの進化です!
インターネットの普及
1990年代後半〜2000年代にかけて、インターネットが一般家庭にも広まり、
誰でも簡単に情報を発信・検索できる時代になりました。
結果、「発信者の独占」が崩壊。個人や小規模メディアも情報発信可能になりました!
スマートフォンとSNSの普及
2000年代後半〜2010年代、スマホとSNS(Twitter・Instagram・YouTube・TikTokなど)が爆発的に普及
これによって、個人が即時に情報を発信できるようになり、そして世界中の人が同時に受信・拡散が可能となり、
「情報の民主化」が起きました。
情報源の多様化。社会的要因
マスメディアの信頼低下
報道の偏り・スポンサー影響・政治的中立性への疑問などから、
「テレビや新聞の情報だけでは不十分」と考える人が増えました。
結果、独立系ニュース・海外メディア・専門家ブログ・SNS情報へと関心が分散。
多様な価値観の台頭
社会がグローバル化・多文化化し、「唯一の正解」が存在しにくくなったため、
人々が自分の立場や興味に合った情報源を選ぶようになりました。
経済構造の変化
YouTuber、ブロガー、インフルエンサーなど、
「情報を発信すること自体が収入になる」仕組み(広告モデル・サブスクなど)が整ったため、
発信者の数が爆発的に増えました。
情報の多様化によって何が起きたのか?
多様な意見や価値観を知り、個人でも発信できるようになった
ひとつの出来事に対しても、国・立場・文化が違えば見方も違う。
情報源が増えたことで、一面的ではない考え方を知ることができます。
例:「環境問題」「戦争」「経済政策」など、海外の意見や個人の体験談からも理解が深まる。
昔は「報道機関」しか発信できませんでしたが、
今は誰でもSNSで発信でき、一般人の声が社会を動かすこともある。
例:災害時の現場情報、企業不祥事の告発、ボランティア活動の拡散など。
フェイクニュースが出たり、偏った情報しか見なくなる可能性が高まった
誰でも発信できる反面、根拠のないデマや誤情報も増えました。
例:「芸能人の偽情報」「災害時の誤報」「健康・投資の詐欺的情報」など。
SNSでは、自分と同じ意見を持つ人の情報ばかり表示されやすい仕組みがあります。
その結果、「自分の考えだけが正しい」と思い込みやすくなる。
例:政治・社会問題などで意見が極端に分かれる原因に。
論文は100%正しい?

論文の定義ってなんだろう
論文(ろんぶん)とは、
あるテーマや問題について、根拠(データ・文献・実験結果など)に基づき、
自分の考え・主張・結論を 論理的に説明した文章 のことです。
簡単に言うと、「自分の考えを証拠を使って筋道立てて説明する文書」です。
| ① 序論(Introduction) | 研究の目的・問題意識・背景を説明 |
| ② 方法(Method) | 調査・実験・分析のやり方を説明 |
| ③ 結果(Result) | 実際に得られたデータや観察結果を示す |
| ④ 考察(Discussion) | 結果の意味を分析し、仮説との関係や他研究との違いを述べる |
| ⑤ 結論(Conclusion) | 研究のまとめ・今後の課題・社会的意義など |
基本的には上記のような構成で記載されています
白い仮説と黒い仮説?
白い仮説とは?
自分が「これは正しいかもしれない」と信じて立てる仮説。
前向きに「証明しよう」という姿勢がある。
新しい発見や理論をつくるときに重要。
例:『カフェインは集中力を高める』
→ 実験やデータでこの効果を確かめようとする。
黒い仮説とは?
「本当にそうだろうか?」という疑いの目で立てる仮説。
反証(否定)することを目的とする。
科学的にはとても大事な視点で、「白い仮説」を壊すことで真理に近づく。
例:「カフェインは集中力を高めない」
→ もし実験結果で“やっぱり高めた”なら、逆説的に白い仮説が強くなる。
科学におけるバランス
科学研究では、「白い仮説(信じる)」と「黒い仮説(疑う)」の両方が必要です。
白い仮説 → 新しい発想を生む。
黒い仮説 → 思い込みを防ぎ、信頼性を高める。
つまり、探求と検証の両輪なんです。
🔹 白い仮説:正しいと思って検証する「創造の仮説」
🔹 黒い仮説:間違いを見つけようとする「批判の仮説」
科学の進歩は、この白と黒の対話によって進んでいきます。
論文によって信憑性が変わる?
論文といっても、全部が同じレベルではありません!!
なぜなら、研究の方法や規模、審査の厳しさがバラバラだからです!
研究の方法に差がある
たとえば
人を対象にした実験(臨床試験)
マウスや細胞だけの実験
ただのアンケート調査
これらは、どれも論文にはなりますが、人に本当に当てはまるかは大きく違います。
つまり、
🧪 実験の質が高いほど → 信頼性が高い
🧫 規模が小さい・条件が甘いほど → 信頼性が低い
| 特徴 | 理由 |
|---|---|
| 査読付きの国際誌(例:Nature, Science, The Lancetなど) | 世界中の専門家による厳しい審査を通過している |
| 被験者数が多い(数百〜数千人) | 統計的に偏りが少ない |
| 再現性がある(他の研究でも同様の結果) | 偶然や操作の可能性が低い |
| 対照群を設けている(比較実験) | 効果を正確に判断できる |
| 利益相反の開示がある | 公平性を保っている |
上記のような論文は比較的信憑性が高いと言われています
正しい情報の見極め方

情報源の確認
信頼できる可能性の高い情報源
発信者が専門家や公的機関
専門知識や責任を持つ立場の人・組織の情報は信頼度が高い。
例:
厚生労働省、消費者庁、WHO、国立研究機関
大学の研究者、医師、専門家団体
「誰が言っているか」を最初にチェックするのが鉄則。
一次情報に近い
口コミやまとめ記事よりも、「元のデータ・論文・統計」に近いものを選ぶ
例:
政府の統計(e-Stat、総務省など)
論文データベース(PubMed、Google Scholar)
企業の公式IR資料(株式情報の場合)
🧠「誰かが要約した情報」より、「誰が出したデータか?」を見る。
複数の信頼できる情報源で一致している
→ 1つの情報だけで判断せず、複数の発信元を比較してみる。
例:
医療情報なら「厚労省+日本医師会+WHO」
経済情報なら「日経新聞+ロイター+Bloomberg」
📊 一致しているほど、偏りが少なく信頼性が高いです!
批判的な見方も必要
誤情報やフェイ棘上筋に騙されにくくなる
理由:出典や論拠を確認する習慣がつくため、根拠のない主張や捏造を見抜ける。
例:SNSで「ある薬が劇的に効く」と見かけても、論文・公的機関の情報を確認して誤報を回避できる。
判断ミスが減り、より良い意思決定ができる
単一情報に飛びつかず、複数の根拠や反証も検討するため、リスクを織り込んだ現実的な判断ができる。
例:投資判断で一つのアナリストレポートだけでなく、業績・業界動向・マクロ指標も確認して損失を避ける。
説得力のある議論・説明ができるようになる
自分の主張を裏付ける一次情報やデータを提示できるので、他者を説得しやすくなる。
例:職場で提案をするとき、根拠データや代替案の評価を示して承認を得やすくなる。
偏見やバイアスに気づきやすくなる
自分の先入観や代表性バイアスなどを意識して検証する習慣がつく。
例:自分が好む情報源だけを信じる「エコーチェンバー」に陥らず、多角的に物事を見るようになる。
学習効率・スキルの向上が早くなる
情報の質を見極められるため、時間をムダにする低品質情報に振り回されず、本質的な学習に集中できる。
例:ダイエット情報の玉石混交を排して、エビデンスのある方法だけを実践することで結果が出やすい。
メンタルの安定
センセーショナルな見出しに流されず、根拠を確認して冷静に対処できる。
例:不安を煽るニュースを見ても、一次情報を見れば過度な心配を避けられる。
長期的なリスク管理能力の向上
短期的な流行や噂に流されず、本質的リスク(構造的な変化)を見極め、備えられる。
例:テクノロジーの長期トレンドを見てスキル投資を行い、将来の失業リスクを下げる。
自分の意見を持とう!
自分の意見を持つことによって、多くの人と議論できたり、その意見の信憑性を自分で調べるようになります!
相手の意見を受け入れられる寛容さをもち、多くの情報や知識を身につけていきましょう😊
~著者情報~
佐野翔吾 Shogo Sano
2000年4月11日生まれ 静岡県出身
趣味:ドライブ🚙/神社巡り⛩️/御朱印集め/サウナ🧖♂️/旅行🛫/映画鑑賞🎥/パン屋さん巡り🥯/紅茶🫖/読書📚